日本の歴史上、最も有名な武家法「御成敗式目」はなにが画期的だったのか? 気鋭の歴史学者・佐藤雄基に訊く
1232年、鎌倉幕府三代執権の北条泰時により制定された初の武家法「御成敗式目」は、日本の歴史上「最も有名な武家法」とも称され、今なお広くその名が知られている。しかし、その内容が詳らかに知られてはいないだろう。
中公新書より刊行された『御成敗式目 鎌倉武士の法と生活』は、同法の主要な条文を詳しく解説、実態や後世への影響を明らかにした一冊だ。著者の佐藤雄基氏に、同書の狙いと「御成敗式目」の先進性について話を聞いた。(編集部)
当時いちばん問題になっていたトピックに合わせて作られている

――「御成敗式目」と言えば、昨年(2022年)放送されたNHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』では坂口健太郎さんが演じていた北条泰時が制定した日本初の「武家法」として有名ですが、今回それをメインに扱った新書を執筆しようと思った、そもそもの動機やきっかけは何だったのでしょう?
佐藤雄基(以下、佐藤):私はもともと日本の中世の法を研究しています。平安時代の終わりから鎌倉時代にかけて……西暦で言うと12世紀、13世紀の人たちが、社会で生じた問題をどのように解決していたかに関心がありました。それを法社会史と史料論の両輪で研究しているのですが、数年前からその中でも特に「御成敗式目」に興味を持っていて、機会があったら何か書きたいと思っていたんです。そしたら編集者の方から、たまたまそういうご提案をいただいて。依頼を受けたのが2020年だったので、『鎌倉殿の13人』に合わせて書いたわけではないのですが、私の遅筆もあって、このタイミングになってしまいました(笑)。
――『鎌倉殿の13人』の最終回で、まさに御成敗式目が登場して……そこで興味を持った方もいるでしょうし、タイミング的にはちょうど良かった気がします(笑)。その具体的な条文については本書の中で詳細に書かれていますが、御成敗式目は端的に言って、どんなところが画期的だったのでしょう?
佐藤:やはりひとつは、オリジナルの法律であったということです。日本の法制度は、8世紀に中国から律令というものを持ってきたところから始まっています。そこから長い年月が経って、明治維新のあと20世紀の終わりに、ヨーロッパの法をモデルにして憲法とか民法とか刑法とかを一気に作るのですが、律令もかなり長いあいだ残っていくし、明治民法というのも今の法律の土台になっていますよね。そうやって外国から体系的なものを持ってきて、それをアレンジしながら長いこと使っていくことが日本の場合はいろいろと多い。仏教とかもそうですよね。
――確かに。
佐藤:鎌倉幕府の人たちは、ついひと世代前までは、関東平野という中央から遠く離れた場所で、何の政治権力もなかった人たちなんです。その彼らが、自分たちで自前の法律を作って、それを中央の人たちにも認めてもらいながら実際に運用していった。しかも、それが単にその時代で立ち消えになるではなく、その後も江戸時代までずっと武士の基本的な法律として残っていきました。それはやっぱり、すごいことだと思うんです。
――ただ、本書の中でも書かれているように、「有名な法」であるにもかかわらず、その具体的な内容については、あまり読まれていないようなところがあって……実際、「神社を修理して、祭礼をきちんと行うこと」から始まっているのは、個人的には少し意外でした。もっと理念的なところから始まるものだと勝手に思っていたので(笑)。
佐藤:そうなんですよね(笑)。有名なわりに、その内容についてはあまり読まれてないし、実は現代語訳もちゃんと出版されていないんです。だから、よく「武家の基本法」みたいな言い方をされていて、本書の副題も最初は「武家の基本法」というのが候補のひとつだったんですけど、「基本法」と言ってしまうと、ちょっと誤解されてしまうというか、今の憲法や刑法、民法みたいなものを想像してしまうんじゃないかと思って。実はそういうものとは少し違っていて……当時すでに、朝廷とか貴族、あとお寺とかがあって、社会の仕組みみたいなものは、ある程度できていたんですよね。そこに武士という新しい人たちが登場して、彼らがいろんなトラブルを起こしていくわけです(笑)。とりわけ、1221年の承久の乱で幕府が朝廷に勝利してからは、東国の武士たちが、守護や地頭として西国に進出していって、現地の荘園領主の権益を脅かしながら、そこでいろいろ揉めたりする。それをどう裁いていくかというところが、式目が作られたひとつの理由だったりするので、当時いちばん問題になっていたトピックに合わせて作られているようなところがあるんです。
――なるほど。確かに「何々をすべきである」「何々はしてはいけない」といった条文もありますけど、やはり土地や所領に関する条文が、とても多い印象があって……。
佐藤:結構、細かいんですよね(笑)。だから法律というよりも、ある意味「マニュアル」みたいなところが、きっとあったんだと思います。こういう場合は、こう判断しようという。ただ、その一方で、それをわざわざ五十一箇条という形で作って、朝廷側にも見せていたりするので、これを基本的なものとしてやっていくという、武士の「マニフェスト」みたいな意味合いもきっとあったと思うんですよね。
法律として読むと、実は悪文
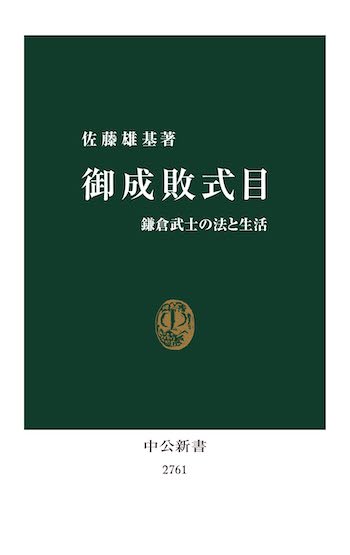
――本書のポイントのひとつとして、条文の具体的な内容や、その背景にある社会状況だけではなく、その「受容の変化」についても触れているところがあるように思いました。
佐藤:やはり、御成敗式目というのは、1232年に制定されたときとそのあとでは、使われ方、受け取られ方の変化がかなり大きいというのが、ひとつ特徴だと思っていて。制定された当時は、先ほど言ったように承久の乱のあとなので、いろいろと細かい揉めごとがいっぱいあったんですよ。ただ、それから月日が経って、五十一箇条全体ではないけれど、その中の特定の条文に関しては、いろいろな人たちに引用されるようになっていきました。それこそ、武士とは何の関係もない百姓たちや寺社関係者たちまでが、それを引用しながら使っていくようになるんです。
――使い勝手が良かったがゆえに、武士だけではなく、他の勢力の人たちからも、広く使われるようになっていった?
佐藤:そうなんです。おそらく幕府としては、いろんな人たちに積極的に使ってもらうためというか、どんどん幕府に訴えてきてくれというつもりで作ったわけではなく、むしろ無根拠な訴えを防ぐため、そういうものを門前払いできるようなルールを作るという部分があったと思うのです。ですが、やっぱり頼りになるというか、とりあえずこれを根拠にして訴えれば、それらしくなるというふうに捉えられたところがあって。
――本来は、幕府の仕事を効率化するために作ったものなのに、いつの間にか幕府の仕事が増えていったという。そのあたりは、現在にも通じる「政策」の難しさですよね(笑)。
佐藤:そうですね(笑)。もちろん、使い勝手が良かったというのは、必ずしも悪いことではなくて、だからこそ、その後も長らく残っていったんだと思うのですが……そう、先ほど「第一条が神社の修復に関するもので驚いた」とおっしゃっていましたけど、今でも神社に行くと、御成敗式目の第一条にある「神は人の敬ひによって威を増し、人は神の徳によって運を添ふ」という一節が、掲げてあったりするんですよ。
――そうなんですね。そうやって使い勝手の良いところを、各勢力が自由に引用しながら残っていったところがあると。
佐藤:そうなんです。だから、先ほど「あまり読まれていない」と言いましたけど、特定の部分に関しては切り取られて、今も残っていたりして。そこが、御成敗式目のすごく面白いところなんですよね。あと、多くの人たちに読んでもらえるように「わかりやすい言葉で書かれた」と言われがちなんですけど、実際に式目を読んでいただいたらわかるように、意外とそうでもないというか(笑)、結構解釈が難しい部分もあって。なので、法律として読むと、実は悪文だったりするんですよね。ただ、だからこそ、「この場合は、どうするんだ?」みたいなことが、その後いろいろ議論されて、諸々補足されながら広がっていったところがあって。
――やはり、その「受容の変化」というところが、本書の肝になるわけですね。
佐藤:そうですね。御成敗式目を制定した北条泰時が生きていた頃はともかく、彼が亡くなったあと、それがどう運用されていったかというのが、ひとつ本書のポイントだと思います。それこそ、中学や高校の教科書だと、「1232年に鎌倉幕府の執権・泰時が、御成敗式目を作りました」で終わってしまって、そのあとのことはよくわからないじゃないですか。やっぱり、それを作ったあとどう使われて、どのように社会的機能を失っていくのかっていうところまで見ないといけないとは思っていて。まあ、式目の場合は、意外と長いあいだ残り続けるわけですが、その「幅」みたいなところを、ちゃんと書いていけたらなっていうのは思っていました。
北条泰時はどんな人物だったのか?

佐藤:そうですね。『吾妻鏡』という鎌倉幕府の歴史書には、ほとんど聖人君子のように描かれていますけど(笑)、1213年の和田合戦とか、1221年の承久の乱では、自ら戦陣に立っている。もともとは、軍人というか武将ですよね。ただ、執権となってからは、御成敗式目の制定をはじめ、政治家としても手腕を発揮しています。ある意味、ナポレオンみたいな感じかもしれないです。自分で戦場に立つけど、法律も作ってしまうという。
――確かに。そう考えると、相当すごい人物だった気がしてきました(笑)。
佐藤:ただ、やっぱりかなり苦労人だったんじゃないかなとは思います。義時の長男ではあるけれど、正室の子ではない庶子なので、家の中では必ずしも盤石な地位ではなかったはずなんですよね。その中で自ら功績を立てることによって、存在感を増していったという。あと泰時は、承久の乱のあと、京都の六波羅に3年ほど赴任しています。北条氏の歴代当主を見ても、京都に赴任したのち、鎌倉に戻って執権となったのは、彼だけなんですよね。
――なるほど。武将でありながら、京都の朝廷や貴族のことも知っていたと。
佐藤:そうですね。『吾妻鏡』には、六波羅から鎌倉に戻ったあと、律令のマニュアル本みたいなものを、毎日読んで勉強していたみたいなことも書いてあります。だから、かなり勉強家というか、努力を怠らない人だったのではないでしょうか。ただ、最近見つかった史料によると、そんな泰時も1225年に北条政子が亡くなったときには、出家したいということを言っていたらしく。要するに、自分の伯母でもある政子という後ろ盾があるからこそ、鎌倉の御家人たちを抑えられていたんだけど、それがなくなったらちょっとまずいんじゃないかっていう。プレッシャーはすごかったと思うんです。ただ、そのあと泰時は、ちゃんと御成敗式目を制定しています。
――先ほど「受容の変化」が本書の肝という話をしましたが、本書の最後の章「現代に生きる式目」では、近代になってから、「象徴天皇制」の起源を御成敗式目に求めるような説も紹介されていて。それには、ちょっと驚きました。
佐藤:そうですよね(笑)。ただ、その大本を辿ると……明治大正ぐらいに、ヨーロッパの情報が、いろいろ日本に入ってくるようになったじゃないですか。そこでイギリスに「マグナ・カルタ(大憲章)」というものがあったことを知るのですが、それと同じ時期に、日本には御成敗式目があったことに気づいて……実際、マグナ・カルタが1215年で、式目が1232年なので、20年ぐらいしか変わらないんですよ。
――そうなんですね。もちろん、そこに直接的な繋がりはないのでしょうが……。
佐藤:マグナ・カルタも最初にできたときは、国王が貴族に対して特権を認めるみたいな感じのものだったのに、近代になってから議会政治や立憲主義のもとになったというふうに、だんだん読み替えられていくんですよね。式目に関しても同じように、戦後になってから、実は日本特有の制度の萌芽がそこにあったという風になっていきます。ヨーロッパをある意味「写し絵」のようにして、式目を再定義していくという。そういう中から、この本でも紹介したように、歴史の研究者以外でも、『「空気」の研究』などで知られる山本七平が『日本的革命の哲学』という本の中で、象徴天皇制の起源を御成敗式目に求めるようなことを書いていたりします。
――そのあたりが、すごく面白いところですよね。本書の中に「歴史は常に生き物のように変化し続け、その時代時代において意味を持たされていく。だから歴史は面白いのだと思う」という一節がありましたが、まさにそういうことですよね。
佐藤:そうですね。「歴史」というと、何年にこういう事件が起きたとか、史実の集積だと思われがちじゃないですか。そうではなくて長いスパンで、ある出来事がその後の社会にどういう影響を与えたのか、どのように変化しながら残っていったのかを捉えることが重要だと思います。御成敗式目のように、色々と読み替えられながら、現代にまでその影響が残っているものがあるということを知ってほしいです。
――本書はどんな読者を想定していましたか。
佐藤:まずは中世、特に鎌倉時代に関心のある人に読んでもらいたいですが、それとは別に、あまり歴史に興味がない人にこそ是非読んでいただきたいと思って書きました。というのも、歴史というのは遠い過去の話で、今の世の中とはあまり関係ないんじゃないかと思えるかもしれないけれど、人間の社会は要所で歴史を参考にしているからです。本書を読むと、それがよくわかるのではないかと思います。
歴史とエンターテインメント
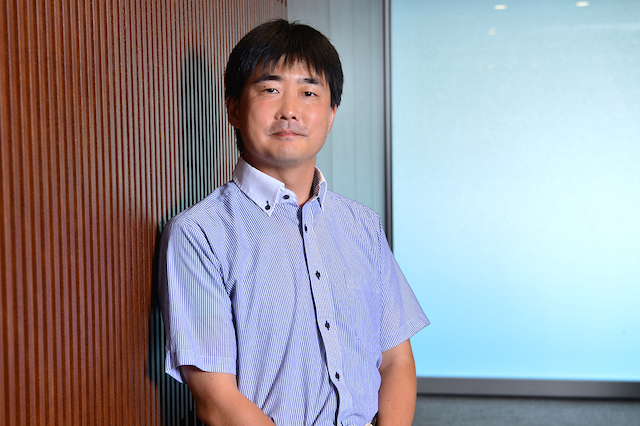
佐藤:中世ブーム自体は、私が大学院生ぐらいの頃から、研究者やコアなファンたちの間でずっと盛り上がっていたと思います。私の周辺では、「室町ブーム」もありましたね。ここ数年は確かに、エンターテインメントの世界まで含めて、中世を扱ったものが増えている印象です。
――その要因は、どこにあると思いますか?
佐藤:1980年代から90年代にかけてはかなり大きな「中世ブーム」があったのですが、それを牽引したのはベストセラーとなった網野善彦さんの『日本の歴史をよみなおす』(1991年)だと思います。網野さんは宮崎駿監督の『もののけ姫』(1997年)にも大きなインスピレーションを与えたと言われていて、近代社会が行き詰まる中、それとはまた違う世界を提示したところが画期的だったのだと思います。網野さんは2004年に亡くなりましたが、僕が歴史の勉強を始めた2000年前後には非常に人気がありました。
ただ、ここ最近の中世ブームがそれと少し違うのは、『もののけ姫』のように中世をある種の「異世界」として捉えるのではなく、もっと等身大の人間の営みを捉えようとしているところです。少し前に大ベストセラーとなった呉座勇一さんの『応仁の乱』(2016年)もそうでしたが、歴史の渦中にいた生身の人間を描こうとしている。「近代」といっても一枚皮をはがせば、いつの時代も変わらないプリミティブ(原始的)な何かがある、そこに目が向いているんじゃないでしょうか。
――なんとなくわかります。『鎌倉殿の13人』も、「異世界」ではなく、今と「地続きの世界」として、感情移入しながら観られていたような気がします。
佐藤:あと、私は1981年の生まれで、子どもの頃からゲームが身近にあったんです。そのため、私の世代では『信長の野望』というゲームをきっかけに歴史に興味を持った人が結構多いんですよ。漫画やアニメも普通に読んだり観たりしている世代なので、そのあたりが上の世代とは視点が違うポイントなのかもしれません。エンターテインメントとの距離感が近いというか。もしかしたら、我々のそういう歴史の捉え方が、昨今のエンターテインメントにも表れているのかもしれませんね。
――最近では、それこそゲームの『刀剣乱舞』とかも無視できない存在ですよね。
佐藤:そうですね。ただ、『刀剣乱舞』だけではなく、歌舞伎などの伝統芸能にしても、本来そういうエンタメ的な側面がある気がします。歴史的な出来事の痕跡を手掛かりにしながら、人々が想像力を膨らませて、広がっていったところがあるわけで。歴史エンターテインメントというのは、いつの時代もそういうものなのかもしれませんね。
■書籍情報
『御成敗式目 鎌倉武士の法と生活』
著者:佐藤雄基
発売日:2023年7月20日
価格:1012円
出版社:中央公論新社
https://www.chuko.co.jp/shinsho/2023/07/102761.html
麦倉正樹
ライター/インタビュアー/編集者。「smart」「サイゾー」「AERA」「CINRA.NET」ほかで、映画、音楽、その他に関するインタビュー/コラム/対談記事を執筆。
0 件のコメント:
コメントを投稿