フェリス阿部教諭「今なお、この本を読むことには大きな意味がある」
フェリス⼥学院では、平和学習として高校1年生の2月に広島研修旅行を実施しています。原爆投下の歴史に加えて放射線が人体に与える影響や、現代の核をめぐる問題についても学びます。研修を通して、核の問題を単に過去の歴史ではなく、⾃分たちが⽣きる現在と未来の問題としてとらえ、平和のために⾃分は何ができるかを考えてほしい――これが私たち教員の願いです。
阿部素子(あべ もとこ) フェリス女学院中学校・高等学校教諭
国際基督教大学高等学校を経て、国際基督教大学教養学部卒業。在学中カリフォルニア大学サンタバーバラ校に留学、アフリカ系アメリカ人の歴史を研究。同校の社会科(地歴・公民科)教諭を経て、2024年4月1日付けで校長に就任
画像のクリックで拡大表示
そんな思いもあって、今回は『 「放射能汚染地図」の今 』(木村真三著、講談社)を紹介します。
著者の木村真三さんは放射線衛生学の研究者。2011年の東日本大震災の発生直後、当時勤めていた研究所から「(震災と福島原発事故に対する)勝手な行動は慎むように」とのメールを受け、住民の避難が最優先のこの非常事態に行動するなとはどういうことか、と辞表を提出してしまいます。
そして、震災3日後にはNHKの取材チームと共に福島に入り、県内各地を車で走り回って放射線量の測定を始めるのです。
原発からどんな放射線核種がどの地域にどれくらい放出されているのか。それを知るために、⽊村さんはひたすら車を走らせ、測定を繰り返します。
測定器の針が振り切れてしまうようなホットスポットが何カ所もあり、中には風に乗って放射性物質が⼤量に降り注いだ地域にある集会所に、住⺠が避難していたケースもありました。
木村さんは、集会所に身を寄せた人々に測定器の数値を見せて説得し、避難を促します。「防護服を着た人たちが何回か(集会所に)来たけれど、誰も線量は教えてくれなかったの」と言う住民。「誰のための情報なのか?」それを肝に銘じておくことが大切だと木村さんは本の中で言っています。
原発事故発生から2カ月間の記録は、NHKの特集番組で「ネットワークでつくる放射能汚染地図」として放送され、大きな話題になりました。
⽊村さんはその後も現場にとどまって⼈々の声を拾い、調査を進めます。科学者の⽴場から⾔えば、全員が避難したほうがいいような場所であっても、どうしても残りたい⼈もいる。残るしかない⼈もいる。⽊村さんは、残るという決断をした⼈たちがその場所で暮らしていく⽅法を共に考え、ときには除染作業を⾏い、⼀緒に汚染地図作りを進めていきます。
こうして人体への被曝(ひばく)の影響の調査や土壌汚染などへの対策のために欠かせない、汚染の実態を詳細に明らかにする放射能汚染地図が作り上げられたのです。
『「放射能汚染地図」の今』(講談社)。「著者である木村真三さんは放射線衛生学の研究者。2011年の東日本大震災の発生直後に福島に入り、汚染の実態を詳細に明らかにする放射能汚染地図を作り上げました」
原発事故はまだ終わっていない
この本の発行は2014年、もう10年も前になります。でも、原発事故はまだ終わっていません。
昨年、木村さんに福島県浪江町の高線量地域を案内していただくという、またとない機会を得ました。以前に、⽊村さんのオンライン講演会に参加したとき「福島を訪れてきちんと学びたいがどうしたらいいか」と質問をしたことがきっかけでした。
除染された県道を⾞で進むと、周囲のあちらこちらにバリケードが張られていました。その奥には廃屋もあれば、すでに取り壊しが進んでいるところも。本の中でもNHKの番組でも紹介されていた、ホットスポットにある集会所にも連れて⾏っていただいたのですが、線量を測ったらいまだにとても⼈が住めない状態でした。13年の⽉⽇が流れているというのに。
このとき、今なお、この本を読むことには⼤きな意味がある、と思いました。あの原発事故で、⽣活を根こそぎ奪われた⼈がたくさんいて、今も故郷に戻れていない。原発事故はまだ終わっていないことを、⽣徒たちに感じてほしいと強く思いました。
13年前といえば、今の中学生がちょうど生まれた頃です。だから当時のことをリアルに知っている生徒はもうほとんどいないんですね。でも、この問題を風化させるわけにはいかないからこそ、私たちが生徒たちに伝えていかなくては。
ということから、今回はこの本を選びました。
大切なのは自分の問題として考えること
やはり大切なのは、自分の問題として考えること、現地の人の側に立って物事を見てみることではないでしょうか。
先ほど広島研修旅行のお話をしましたが、核と平和について考えるためには、被爆した人に思いをはせ、体験を知ることが欠かせないと思います。
ですから研修旅⾏では、広島平和記念資料館の⾒学のほか、平和公園内外の碑を案内してくださる広島⼥学院の⽣徒さんと交流したり、現地の研究者やジャーナリスト、そして被爆者の方々からお話を聞いたりする機会を設けています。
広島へ⾏く前の事前学習として夏休みに戦争や核に関するブックリストを渡しています。これは社会科の教員が研修旅⾏の前に⽣徒たちにぜひとも読んでもらいたい本を持ち寄ってリスト化したもの。リストから2冊以上読んで、⾃分の意⾒をまとめることが夏休みの課題です。
そして、広島に落とされた原子爆弾は、核時代の始まりをも意味します。「科学者と核」「戦後の核開発や核軍縮」「核問題の現状」など関心のある切り口で、グループに分かれて調べることがもう一つの事前課題です。クラス内で発表し、中から選ばれたグループが広島女学院との交流会の場でも発表します。
広島⼥学院はフェリス⼥学院と同じミッション・スクール。当時、原爆により生徒や教員など多くの犠牲者が出てしまった悲劇を受けて、素晴らしい平和教育を実践なさっています。そして、交流会ではその様々な取り組みを発表してくださるのです。
フェリスの⽣徒は、「本を通して向き合い考えたこと」を発表する形になり、刺激をいただくことばかりの交流会ですが、あちらもとてもいい機会だと⾔ってくださって、もうずっと続いています。
生徒たちには、もっと本に出合ってほしい
最後に『「放射能汚染地図」の今』に戻って、なぜ生徒たちにこの本を読んでもらいたいと思ったのか、その理由をもう一つお話しします。
私はテレビのドキュメンタリー番組が好きで、日頃から、これはというものは録画して授業でも生徒に見せることがあります。社会問題を考える入り口として、やはり映像は分かりやすいし、よくできた作品であるほど、作り手の問題意識がストレートに伝わってきて理解もとても深まります。
この本も、先ほどお伝えしたように、木村さんが福島入りしてからの最初の2カ月間については、NHKの番組として放送されました。今何が起きているのかを知るうえでは素晴らしい番組でしたが、それでも私は生徒たちには映像だけでなく、本にも出合ってほしいと思うのです。
なぜなら、ここには、木村さんが何のために、誰のためにここまでのことを成し遂げてきたのか、今もやり続けているのか、研究者としての生きざまが丁寧に書いてあるから。
映像作品のように一瞬でパッと入っていけるものではないけれど、じっくり読めば著者の生きる姿勢が、一人ひとりの中に浸透して広がっていく。何が心に響くのかは人それぞれでしょう。だから、こちらが思う以上のものが、読み手の中で豊かに実る可能性だってある。
もしかしたら、これが生徒に本を薦めたくなる理由なのかもしれません。
「生徒たちには映像だけでなく、本にも出合ってほしいと思います。映像作品のように一瞬でパッと入っていけるものではないけれど、じっくり読めば著者の生きる姿勢が、一人ひとりの中に浸透して広がっていくからです」
画像のクリックで拡大表示
取材・文/平林理恵 写真/稲垣純也

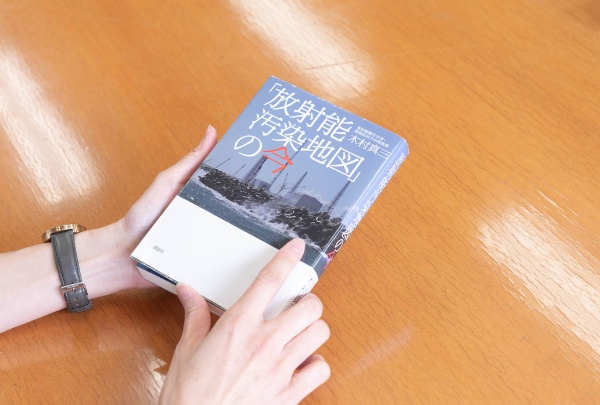



0 件のコメント:
コメントを投稿