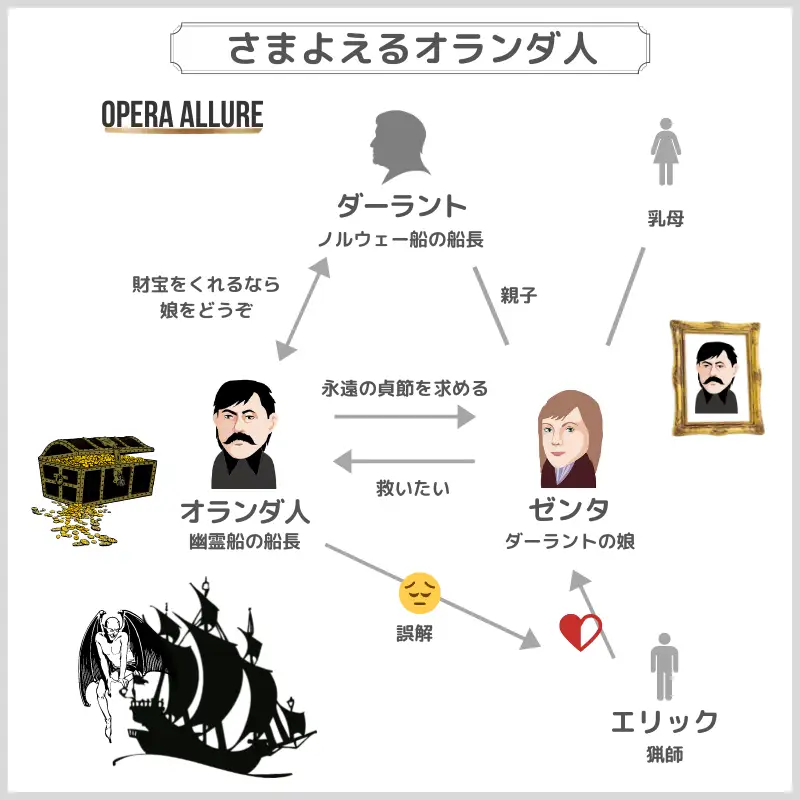ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』を解読する マックス・ヴェーバー 『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』は、社会学者マックス・ヴェーバー(1864年~1920年)の代表作だ。1905年に発表された。ヴェーバーには多くの著作があるが、ヴェーバーといったらコレ!というくらい知名度は高い。
『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』のテーマは、近代資本主義の起源だ。なぜ中国や日本ではなく、また古代メソポタミアやギリシアではなく、ヨーロッパ近代において資本主義が成立するに至ったのか。またその条件は何か。 これが本書のメインテーマだ。
「プロテスタンティズムが資本主義の本質だ」とは言っていない 先入観をもっていたり膨大な知識に圧倒されたりすると、しばしば私たちはそれらの内容を細かく吟味せず、雑に受け取ってしまうことがある。
本書に関して言えば、「ヴェーバーはプロテスタンティズムが資本主義の中心にあると考えた」と解釈されることがとても多い。
たとえば、コラム:宗教学と経済学から見た欧州債務危機の深層=上野泰也氏 | 日銀特集 | Reuters に次のような見方が紹介されている。
中央大学総合政策学部の保坂俊司教授は、ユーロ危機を引き起こした当事国が総じてカトリック国(あるいは非プロテスタント系)であることに着目し、欧州債務危機の根源に倫理観、特に経済倫理の違いがあるとの指摘を行っている(「週刊エコノミスト」2012年6月19日号掲載論文「宗教の歴史 カトリックとプロテスタント 欧州危機が示す倫理観の差」)。
この見方は明らかにヴェーバーの議論を意識したものだが、率直に言って、こうしたヴェーバー解釈は正しくない。というのもヴェーバーは、プロテスタント的な世俗的禁欲は初期の資本形成において一定程度の役割を果たしたが、それと同じく(むしろそれ以上に)重要だったのは、専門官僚制と合理的法律をもつ合理的国家の存在だったと考えていたからだ。
というよりも、仮に経済倫理の「違い」が欧州債務危機を生み出しているというのであれば、カトリックであれプロテスタントであれ、どちらか一方が不景気になると同時に、他方は好景気になっていてもおかしくない。しかし実際はヨーロッパが全体としてあまり景気がよくないわけだから、その点ですでに議論として足りないことは想像がつく。
資本主義経済は様々な要因(経済学的、社会学的、会計学的…)から構成されているので、どこかに決定的な要因があるわけではない。そんなものを見つけようとするのは最初から無理な試みなのだ。
逆説でもない また、念のために確認しておくと、ヴェーバーは別にプロテスタンティズムと資本主義の関係を「逆説的」と考えていたわけではない。というか、そもそもそう考えるはずがない。なぜならヴェーバーはそこに合理性という名の架け橋を見ていたからだ。逆説的に見えるのはアナタに先入観があるからだ。「宗教が資本主義の原動力になるはずがない」という先入観が…。
では本文について見ていこう。
「資本主義の精神」と「天職」の観念 ベンジャミン・フランクリン ヴェーバーによれば、近代資本主義を成立させた原動力は、資本主義の精神にある。では資本主義の精神とは何か?ヴェーバーはその原型をベンジャミン・フランクリンに求めている。
フランクリンは、かの有名な「時は金なり」Time is money という表現で知られるアメリカの作家・政治家だ。アーレントが『革命について』 で取り上げていたジョン・アダムズやトマス・ジェファーソンと並ぶ「アメリカ建国の父」のひとりであり、現在の米100ドル紙幣にはフランクリンの肖像が使われている。発明家でもあり、凧を使った実験で雷が電気であることを発見したことでよく知られている。
そんなフランクリンのどこに資本主義の精神が認められるのだろうか?ヴェーバーは次のように言う。
「時間は貨幣であることを忘れてはならない。一日で10シリング稼げるのに、遊んだり怠けたりして半日過ごすような人は、実際には6ペンスしか娯楽に使っていないとしても、最低5シリングはドブに捨てているに等しいのだ」。このようにフランクリンは私たちに説く。
これと対照的なのが、中世ドイツの大富豪ヤコブ・フッガーだ。フッガーはすでに引退した同業者から「そろそろ引退したらどうだ?」と忠告されたとき、これを退け、「生きている間は出来るだけ儲けてやろうと思っているぜガハハ」的に答えたといわれている。
フッガーの場合は、商人的な冒険心の表明にすぎないのに対して、フランクリンの場合には、倫理的な生活原則 という性格を帯びている。
私は本書で「資本主義の精神」という概念を、フランクリン的な意味合いで使うことにしようと思う。確かに資本主義は中国やインド、バビロンにも、また古代にも中世にも存在していた。しかしそのいずれにもフランクリン的な「精神」は存在しなかった。この精神が、それら資本主義と、近代ヨーロッパ的資本主義を分けるひとつの本質的な要素なのだ。
「天職」 ヴェーバーによれば、フランクリン的な「精神」において中心的な役割を果たしていたのが「天職 」(Beruf, calling)の観念だ。
ベンジャミン・フランクリンの例に見たような、正当な利潤を》Beruf《「天職」として組繊的かつ合理的に追求するという心情を、われわれがここで暫定的に「(近代)資本主義の精神」と名づけるのは、近代資本主義的企業がこの心情のもっとも適合的な形態として現われ、また逆にこの心情が資本主義的企業のもっとも適合的な精神的推進力となったという歴史的理由によるものだ。
ヴェーバーによれば、ここにカトリック(フッガー)とプロテスタンティズム(フランクリン)の根本的な違いがある。
プロテスタンティズムとカトリックを分かつ本質的な差異は、プロテスタンティズムが世俗内で義務を遂行することを、神より与えられし「召命」Beruf と見なした点にある。
Beruf はドイツ語で職業を意味する。それと同時に、そこには神から与えられた使命という意味も込められている。つまりプロテスタントにとっては、自分がいま生きている社会のうちで勤勉に働くことが神の意志に最もかなうことになる。
ルターから始まったプロテスタンティズム マルティン・ルター プロテスタンティズムは、16世紀のヨーロッパに起こった宗教改革運動を通じて、カトリック教会から分離した諸教派のことだ。代表的なものに、ルター派、カルヴァン派、国教会などがある。
宗教改革運動は、マルティン・ルターらがカトリック教会の改革を求めて起こしたものだ。
当時のカトリック教会では、罪の償いを軽減するためと称して「免罪符」が発行されていた。カネを払って免罪符を購入すれば、ローマへ巡礼せずとも罪は許されるという論理だ。
これに対して、ルターは、本当にそうなのか、と考えた。ルターは「内的な信仰のみが人間を義(正しい)とする」という確信を抱いており、免罪符が罪を償うとはどうしても納得できなかったのだ。
そこでルターは、免罪符の正当性に対する疑問を『95カ条の論題』にまとめ、これをヴィッテンベルク大学の聖堂の扉に張り出した。もともとルターはこれを神学の議論の枠内で捉えていたため、ラテン語で書かれていたが、ドイツ語に翻訳された後、またたく間にヨーロッパ全土へと広がっていった。この事件をきっかけとして宗教改革運動が始まったとされている。
天職の観念はルターに由来 ヴェーバーによれば、天職の観念はルターに由来した。世俗の内で義務を遂行すること、これが神の意志にかなうのだと考えられるようになった。しかしルターは、あくまで世俗における労働を道徳的に重視しただけであり、資本主義とその「精神」につながるような見方を打ち出したわけではない。結局ルター自身は伝統主義を脱することはできなかった。そうヴェーバーは言う。
彼の経済的伝統主義は、最初はパウロ的な無関心的態度の結果だったのに、のちには、いよいよその度を加えてきた摂理の信仰に基づくものとなり、神への無条件的服従と所与の環境への無条件的適応とを同一視するにいたった。このようにして、ルッターは結局、宗教的原理と職業労働との結合を根本的に新しい、あるいはなんらかの原理的な基礎の上にうちたてるにはいたらなかった。
このようにして、ルッターの場合、天職概念は結局伝統主義を脱するにいたらなかった。
カルヴィニズムの「予定説」 ジャン・カルヴァン ヴェーバーによれば、資本主義の発達に役割を果たしたのは、ルター派よりもむしろカルヴィニズム(カルヴァン派) だ。
カルヴィニズムは、フランス出身の神学者ジャン・カルヴァンが創始した教派だ。カルヴァンは、ルター派など一部の教派を除き、多くのプロテスタント諸派に影響を及ぼした。
ヴェーバーによれば、近代資本主義の精神に影響を及ぼしたのは、カルヴィニズムの「予定説」だ。これは、自分が救済されるかどうかは、生まれる前にすでに神によって決められてしまっているとする教義であり、カルヴァン神学の中心教義であるとされている(異論もあるが、少なくともヴェーバーはそう考えている) 。
カルヴィニズムにおいては、神のために人間があるとされる。カルヴァン派信徒は「神の栄光を増すため」に現世で労働を行う。彼らは、神が社会的秩序を実益に役立つように創造したので、実益に役立つ労働はまさに神の意にかなうと考えたのだ。
カルヴァン派信徒が現世においておこなう社会的な労働は、ひたすら ≫ in majorem gloriam Dei ≪「神の栄光を増すため」のものだ。だから、現世で人々全体の生活のために役立とうとする職業労働もまたこのような性格をもつことになる。
救済の確信を生活の合理化によって生み出した ところで、カルヴァン派信徒は、予定説をどのように受け止めたのだろうか。中には「神の思すままに」と、何の迷いもなく信仰し続けた信徒もいるかもしれない。しかし多くの信徒たちは深い孤独の感情を抱いていたはずだ。
そうした教義を信徒たちはどのように耐え忍んだのか?おそらく彼らは、自分が救われていることを確信するための方法を求めたにちがいない。強い信仰心で確証するよう求めるのは、次第に不可能になっていった。
そこで彼らは、自分自身を審査することによって、救いの確信を作り出した。 救済は懺悔ではなく、生活に計画性と組織性を取り入れることによって初めて可能となる。そのように考えた彼らは、自分の生活を徹底的に合理化するように促された。
こうして、人々の日常的な倫理的実践から無計画性と無組織性がとりのぞかれ、生活態度の全体にわたって、一貫した方法が形づくられることになった。
「聖徒」たちの生活はひたすら救いの至福という超越的な目標に向けられた。が、また、まさしくそのために現世の生活は、地上で神の栄光を増し加えるという観点によってもっぱら支配され、徹底的に合理化されることになった。
そのためには合理的な禁欲 が必要であり、合理的な禁欲のためには生活態度を合理的に秩序づける必要がある。彼らの禁欲は、まったく世俗的なものだった。
かくして信徒たちは職業生活のうちで禁欲的な生活を営む必要に迫られた。そうした態度の規範は聖書、とくに旧約聖書の律法に求められた。彼らの合理的な性格はそこに由来している。こうしたカルヴィニズムの生活態度は、後期ピューリタンでは「現世生活全体のキリスト教化」にまで押し進められた。
要約すると次のようになる。信徒たちは「自然のままの人間」がなしうる以上の行為によってしか救済は保証されないと考えた。このことが彼らに、自身の生活を禁欲的に統御するよう動機づけた。こうした世俗内での生活態度の合理化は、まさに天職の観念が作り出したのだ。
この禁欲的な生活のスタイルは、すでに見たとおり、神の意志に合わせて全存在を合理的に形成するということを意味した。しかも、この禁欲はもはやopus supererogationis (義務以上の善き行為)ではなくて、救いの確信をえようとする者すべてに要求される行為だった。こうして、宗教的要求にもとづく聖徒たちの、「自然の」ままの生活とは異なった特別の生活は—これが決定的な点なのだが—もはや世俗の外の修道院ではなくて、世俗とその秩序のただなかで行われることになった。このような、来世を目指しつつ世俗の内部で行われる生活態度の合理化、これこそが禁欲的プロテスタンティズムの天職観念が作り出したものだったのだ。
「天職」と合理的禁欲が資本形成をもたらした さて、プロテスタンティズムの教義によれば、労働とは神の栄光のためになされねばならない天命である。神の意志を地上で成し遂げんとする努力、これが職業労働だ、と教徒たちは考えた。
そこで重要な役割を果たしたのが天職観念と合理的禁欲だ。それらは「衝動的な快楽」を敵視し、財の獲得を伝統主義的な倫理から解放した。禁欲は世俗における利潤の獲得を正当化しただけでなく、それが神の意志にかなうと考えた。禁欲は教徒たちをして、世俗において神の意志を実現するよう向かわせたのだ。
こうして次のことが帰結する。獲得した財は原則的に投下資本として使用された。合理的禁欲の観念は、節制の強制による資本形成をもたらしたのだ。
プロテスタンティズムの世俗内的禁欲は、所有物の無頓着な享楽に全力をあげて反対し、消費を、とりわけ奢侈的な消費を圧殺した。その反面、この禁欲は心理的効果として財の獲得を伝統主義的倫理の障害から解き放った。利潤の追求を合法化したばかりでなく、それを(上述したような意味で)まさしく神の意志に添うものと考えて、そうした伝統主義の桎梏を破砕してしまったのだ。
さきに述べた消費の圧殺とこうした営利の解放とを一つに結びつけてみるならば、その外面的結果はおのずから明らかとなる。すなわち、禁欲的節約強制による資本形成がそれだ。利得したものの消費的使用を阻止することは、まさしく、それの生産的利用を、つまりは投下資本としての使用を促さずにはいなかった。
ヴェーバーいわく、近代資本主義の精神が、資本主義における企業に最適な精神的推進力として働いた。企業活動から得られる利潤を享受する代わりに積極的に再投資へと回すプロセスは、利己心の立場からすると不合理のように見える。しかし、実際にそこに携わっている人にとって、これはきわめて合理的なプロセスだったのだ。そうヴェーバーは言う。
プロテスタンティズムの倫理を資本主義の「原因」と見なすのは× 本書の全体像を再確認すると、こんな感じだ。
近代資本主義が成立するには、プロテスタンティズム、正確に言うとカルヴィニズムのエートス(心的態度)が大きな役割を果たした。その際に重要な意味をもっていたのが、カルヴィニズムの「予定説」、つまり自分が救われるかどうかは生まれる前にすでに神によって決められてしまっているという教説だ。カルヴァン派の教徒は、救いの確証を得るために、みずからの生活を徹底的に組織化し、禁欲的なものとした。この合理的禁欲による節約が、財を投下資本として使用するよう促し、資本形成をもたらした。
ヴェーバーいわく、合理的禁欲と生活態度の合理化をもたらしたカルヴィニズムのエートスが、近代資本主義の原動力として働いた。その意味で、合理性こそが近代資本主義の精神の形式である。そうヴェーバーは考えた。
キリスト教が資本主義の出発点にあると言われると、かなりのインパクトがある。一瞬逆説的に聞こえるが、ヴェーバーからすればそこには何の逆説もない。宗教は資本主義を否定するに違いないと考えるのは根拠のない憶測だ、というわけだ。
本書は、経済が宗教を規定するというマルクスの「上部-下部構造」論に対する反論としての意義をもっていた。財の交換が近代的資本主義の成立に直結するわけではない、だが、私自身が最初読み間違えていた点だが、念のために言うと、ヴェーバーは、プロテスタンティズムの精神がいまある資本主義体制を支えていると主張しているわけではない。しかも、それはあくまで諸要素のうちのひとつ でしかない。ヴェーバーはハッキリ書いている。
もちろん、現在の資本主義が存続しうるための条件として、その個々の担い手たち、たとえば近代資本主義的経営の企業家や労働者たちがそうした倫理的原則を主体的に習得していなければならぬ、ということでもない。今日の資本主義的経済組織は既成の巨大な秩序界であって、個々人は生まれながらにしてその中に入りこむ … 誰であれ市場と関連をもつかぎり、この秩序界は彼の経済行為に対して一定の規範を押しつける。
今日では、禁欲の精神は—最終的にか否か、誰が知ろう—この鉄の檻から抜け出してしまった。ともかく勝利をとげた資本主義は、機械の基礎の上に立って以来、この支柱をもう必要としない。
いったん資本主義体制が成立してしまった以上、個々人はただ資本主義の制度のうちへと参加するにすぎず(もちろん他の選択肢もありうるが)、プロテスタンティズムの倫理を身につけておく必要はない。その意味で、プロテスタンティズムの倫理が現在の資本主義を支えているわけではない。そうヴェーバーは言うわけだ。
色々な要素が絡んでいる では一体何が近代資本主義を支えているとヴェーバーは考えているのだろうか?
ここで、『経済と社会』に所収されている「国家社会学」の議論が参考になる。ヴェーバーはそこで、近代資本主義は専門官僚制と合理的法律をもつ合理的国家でのみ育つと論じていた。
近代資本主義は、ただ合理的国家においてのみ育つのである。それは、専門的官僚制と合理的法律を基礎として育つものである。
資本主義に必要なのは、機械の如く計算の可能な法律である。
これを逆に言うと、そうした条件を満たしていさえすれば、国内においてプロテスタンティズムが強い勢力をもっているかどうかに関係なく、資本主義経済は成立しうる。
また、あまりに当たり前なのであえて指摘されることはほとんどないが、複式簿記のような会計技術や株式の制度がなければ、資本主義経済がここまで大きくなることはなかったはずだ。資本主義経済は、さまざまな要素が絡んだ複合的な営みだ。資本主義に単一の原因があると考えるのは表象的であり、概念的ではない。
確かに、「プロテスタンティズムの倫理が資本主義の起源だ」と言えば、もうそれ以上考えなくてよくなるので、ラクと言えばラクだ。しかしそうした単純な図式化こそ、ヴェーバーがマルクス主義の唯物史観に対して強く批判していたことは、頭の片隅に置いておくとよいだろう。